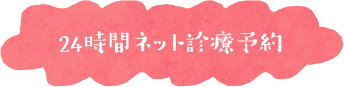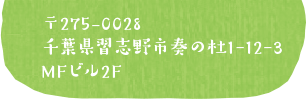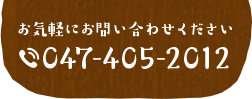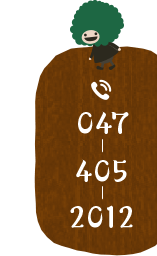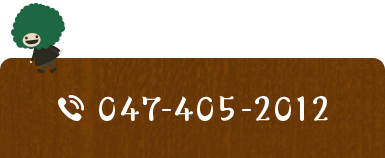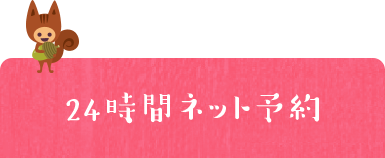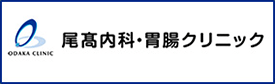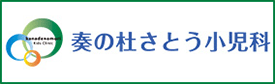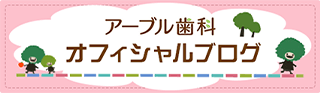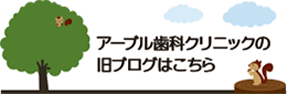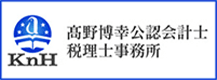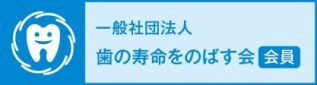小児矯正の治療期間を知りたい方へ〜年齢によって異なる治療内容と期間
お子さんの歯並びが気になり始めたとき、多くの保護者の方が「いつから始めるべきか」「どのくらいの治療期間がかかるのか」と不安を感じられます。特に小児矯正は子どもの成長に合わせて進めていくため、年齢によって治療内容や治療期間が大きく変わってきます。
小児矯正は早期に始めることで、将来的な歯並びや咬み合わせの改善だけでなく、顎や歯の健全な成長にも繋がります。しかし、その治療期間は子どもの成長速度や歯並びの状態によって個人差があります。
「矯正治療に早すぎることはない」というのが私たち歯科医師の考えです。お子さんの状態によって最適な治療開始時期は異なりますが、早い段階でお口の状態を確認することで、より効果的な治療計画を立てることができます。
- 小児矯正はいつから始める?適切な開始時期と年齢別の特徴
- 小児矯正の治療期間はどのくらい?年齢別の目安
- 永久歯列完成期の矯正治療(12歳以降):第二期治療
- 小児矯正で対応できる歯並びの問題
- 小児矯正の治療期間に影響する要因
- 小児矯正の治療期間を短くするためのポイント
- まとめ:小児矯正は早期発見・早期治療が鍵
小児矯正はいつから始める?適切な開始時期と年齢別の特徴
小児矯正の開始時期は、お子さんの成長段階と治療を受けられる状態かどうかが大きく関わってきます。一般的に、6〜7歳頃から始めるのが早い時期とされています。この時期は乳歯から永久歯への生え変わりが始まる時期であり、歯並びを改善するための様々な予防措置や誘導が行える重要な時期です。
日本人は欧米人に比べて顎が小さい傾向があり、歯が生えるスペースが確保できないことで歯並びが乱れることが多いのです。そのため、永久歯が生え揃う前に適切な処置を行うことが重要になります。
では、年齢別に小児矯正の特徴を見ていきましょう。
0〜4歳(乳歯期):観察と習慣づけの時期
この時期は頭や顎の骨、体の成長が著しい時期です。授乳や離乳食を通じて、お口周りの筋肉が自然と発達していきます。それとともに鼻呼吸も身につき、嚥下機能も向上します。
0〜4歳のお子さんには、通常、矯正装置を使用した治療は行いません。この時期は、お子さんとの笑顔の多いスキンシップを大切にし、よく食べよく飲み、健やかな成長を支えることが重要です。
ただし、指しゃぶりや舌の癖などが気になる場合は、早めに歯科医院に相談することをおすすめします。これらの習慣は将来的な歯並びに影響を与える可能性があるからです。
5〜7歳(乳歯から永久歯への交換期):第一期治療の開始時期
5〜7歳頃は、前歯が生え変わる時期であり、小児矯正を始める適切なタイミングとされています。この時期から始める矯正方法では、取り外しの矯正装置(プレート)を装着し、正しい歯並びや咬み合わせのバランスを整えていきます。
特に、受け口(反対咬合)や奥歯の噛み合わせがずれている(交叉咬合)場合は、できるだけ早く治療を開始する必要があります。これらの問題は放置すると、顎の成長に悪影響を及ぼし、将来的に外科矯正が必要になる可能性もあるのです。
当院ではプレオルソというお子さんの歯並びや噛み合わせを改善するために開発された、マウスピース型の矯正装置もご用意しております。
小児矯正の治療期間はどのくらい?年齢別の目安
小児矯正の治療期間は、お子さんの成長速度や歯並びの状態によって個人差がありますが、年齢別におおよその目安をお伝えします。
乳歯期から始める矯正(5〜7歳頃):1〜3年程度
この時期に始める矯正治療は「第一期治療」と呼ばれ、顎の成長を促し、永久歯がきれいに並ぶためのスペースを確保することが目標となります。治療期間は一般的に1〜3年程度ですが、お子さんの成長に合わせて調整していきます。
取り外し式の装置を使用することが多く、1〜2ヶ月に一度の通院が必要です。この時期に適切な治療を行うことで、永久歯が生え揃った後の「第二期治療」が不要になる場合もあります。
当院では、この時期の矯正治療として、拡大床装置やプレオルソなどの装置を使用しています。特にプレオルソは、歯列矯正用咬合誘導装置として、お子さんの歯並びを自然に誘導する効果があります。
混合歯列期の矯正(8〜12歳頃):1〜2年程度
乳歯と永久歯が混在する時期の矯正治療も、「第一期治療」に含まれます。この時期は骨格の成長を積極的にコントロールする最も重要な時期です。
上顎が小さいお子さんには、上顎の成長を促す装置を使用し、逆に上顎が大きいお子さんには、上顎の成長を抑制する装置を使用します。治療期間は一般的に1〜2年程度ですが、歯並びの状態によって異なります。
8歳以上のお子さんには、当院ではインビザライン・ファーストという、お子さん向けのマウスピース矯正も提供しています。従来のワイヤー矯正に比べて目立ちにくく、取り外しも可能なため、お子さんの負担が少ないのが特徴です。
永久歯列完成期の矯正治療(12歳以降):第二期治療
永久歯が生え揃う12歳以降の矯正治療は「第二期治療」と呼ばれます。この時期は、歯並びを細かく調整し、美しい歯列と機能的な咬み合わせを完成させることが目標です。
永久歯列完成期の治療期間:2〜3年程度
第二期治療では、主にワイヤー矯正やマウスピース矯正を使用します。治療期間は一般的に2年6ヶ月〜3年程度(30〜36回の通院)が目安ですが、歯の移動には個人差があるため、お子さんの状態によって変わってきます。
当院では、透明なブラケットを使用したワイヤー矯正や、カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン)など、お子さんの年齢や生活スタイルに合わせた矯正方法をご提案しています。
第二期治療では、1〜2ヶ月に一度の通院が必要です。治療の進行状況に応じて、装置の調整やワイヤーの交換を行います。
歯並びの乱れは、咬み合わせのバランスを崩す原因になります。食べ物をしっかり噛み切れずに消化不良を引き起こし、十分な栄養の摂取が難しくなり、健やかな成長を阻害してしまうこともあります。また、思春期の学生であれば、見た目にコンプレックスを抱えやすく、人前で話したり笑ったりすることを避けてしまうようになることもあるのです。
小児矯正で対応できる歯並びの問題
小児矯正では、様々な歯並びの問題に対応することができます。当院で対応可能な主な歯並びの悩みをご紹介します。
出っ歯(上顎前突)
上の前歯が前に出ている状態です。見た目の問題だけでなく、口が閉じにくい、前歯で物を噛み切りにくいなどの機能的な問題も生じます。早期に治療を始めることで、顎の成長をコントロールしながら改善することができます。
受け口(反対咬合)
下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態です。放置すると顎の成長に悪影響を及ぼし、成人になってからの治療が難しくなる場合があります。できるだけ早期(5〜7歳頃)に治療を開始することが重要です。
すきっ歯(空隙歯列)
歯と歯の間に隙間がある状態です。見た目の問題だけでなく、食べ物が詰まりやすいなどの問題もあります。原因によって治療方法が異なりますが、適切な装置を使用して改善することができます。
開咬(かいこう)
上下の前歯が噛み合わない状態です。舌の癖や指しゃぶりなどが原因となることが多く、これらの習慣を改善しながら矯正治療を進めていきます。
八重歯(叢生)
歯が重なって生えている状態です。顎のスペースが足りないことが主な原因で、場合によっては抜歯が必要になることもあります。早期に治療を始めることで、顎の成長を促し、抜歯を避けられる可能性が高まります。
交叉咬合(こうさこうごう)
通常、下の歯は上の歯の内側にありますが、それが一部反対になっている状態です。放置すると顎が横にずれて成長してしまう恐れがあるため、できるだけ早期に治療を開始する必要があります。
小児矯正の治療期間に影響する要因
小児矯正の治療期間は、様々な要因によって変わってきます。主な影響要因をご紹介します。
歯並びの状態と重症度
歯並びの乱れが軽度であれば治療期間は短くなり、重度であれば長くなる傾向があります。特に骨格的な問題を伴う場合は、治療期間が長くなることが多いです。
例えば、単純な前歯のすきっ歯であれば数ヶ月で改善することもありますが、顎の大きさに問題がある場合は、成長に合わせた長期的な治療が必要になります。
治療開始年齢と成長速度
お子さんの成長速度も治療期間に大きく影響します。成長が早いお子さんは治療効果も現れやすく、治療期間が短くなる傾向があります。逆に、成長が遅いお子さんは治療期間が長くなることがあります。
また、治療開始年齢も重要です。適切な時期に治療を始めることで、顎の成長をうまく利用した効率的な治療が可能になります。一般的に、早期に始めるほど治療期間が短くなる傾向がありますが、個人差があるため一概には言えません。
装置の種類と使用状況
使用する矯正装置の種類によっても治療期間は変わります。固定式の装置(ブラケットとワイヤー)は効率的に歯を動かせますが、取り外し式の装置は装着時間によって効果が左右されます。
特に取り外し式の装置は、指示通りに装着しないと治療効果が得られず、結果的に治療期間が長くなってしまいます。お子さんの協力度も治療期間に大きく影響するのです。
小児矯正の治療期間を短くするためのポイント
小児矯正の治療期間をできるだけ短くするためには、いくつかのポイントがあります。
適切な時期に治療を開始する
お子さんの歯並びや顎の状態に応じた適切な時期に治療を開始することが重要です。早すぎても遅すぎても効率的な治療ができないことがあります。まずは矯正歯科医に相談し、お子さんに最適な治療開始時期を見極めましょう。
当院では矯正無料相談を実施していますので、お子さんの歯並びが気になる方は、お気軽にご相談ください。
指示通りに装置を使用する
特に取り外し式の装置は、指示された時間でしっかり装着することが重要です。装着時間が不足すると治療効果が得られず、結果的に治療期間が長くなってしまいます。
お子さんが自分で管理するのが難しい場合は、保護者の方がサポートしてあげましょう。装置の使用状況を記録するカレンダーなどを活用すると良いでしょう。
定期的に通院する
予約された通院日はできるだけ守りましょう。通院をキャンセルしたり延期したりすると、その分だけ治療期間が延びてしまいます。
当院では、お子さんが退屈しないようにユニットにタブレットを設置したり、ボーネルンド社プロデュースの遊び場を用意したりと、お子さんが楽しく通院できる工夫をしています。
まとめ:小児矯正は早期発見・早期治療が鍵
小児矯正の治療期間は、お子さんの年齢や歯並びの状態によって異なりますが、一般的には以下のような目安があります。
- ・乳歯期から始める矯正(5〜7歳頃):1〜3年程度
- ・混合歯列期の矯正(8〜12歳頃):1〜2年程度
-
・永久歯列完成期の矯正(12歳以降):2〜3年程度
小児矯正は「早期発見・早期治療」が重要です。お子さんの歯並びや顎の成長に問題がある場合、早めに専門医に相談することで、より効果的な治療が可能になります。
当院では「矯正治療に早いはありません」という考えのもと、お子さんの状態に合わせた最適な矯正治療をご提案しています。まずは無料矯正相談にお越しいただき、お子さんの歯並びの状態を確認してみませんか?
アーブル歯科クリニックでは、お子さん専用の診療室やキッズスペースを用意し、できるだけ怖くない、痛くない診療を心掛けています。お子さんの健やかな成長と美しい笑顔のために、ぜひ一度ご相談ください。詳しい情報や無料相談のご予約は、アーブル歯科クリニックのウェブサイトをご覧ください。

-
著者情報
- アーブル歯科クリニック 院長 田中 雄一
-
略歴
- 2007年日本大学松戸歯学部卒業
- 2007年日本大学松戸歯学部附属病院 臨床研修医
- 2008年~2014年一般開業医勤務
- 2014年アーブル歯科クリニック開院
-
所属団体
- 日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座 非常勤
- 日本口腔インプラント学会
- 日本顎咬合学会
- 日本臨床歯周病学会
- AICインプラント専門医
- BPSデンチャークリニカル 認定医
- スウェーデン歯科学会
- 口腔感染症予防外来認定医
- POIC研究会 ホームケアアドバイザー認定
- 私立アスクかなでのもり第二保育園 嘱託医
- ブレーメン津田沼保育園 嘱託医
- リトルガーデンインターナショナルスクール新習志野校 嘱託医
- クニナ奏の杜保育園 嘱託医
- 習志野市立谷津小学校 学校歯科医
-
矯正医
- 田中 慶子
-
所属団体
- 日本矯正歯科学会 認定医
- インビザライン 認定医