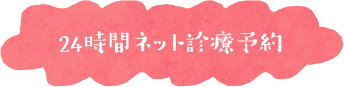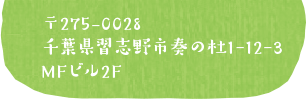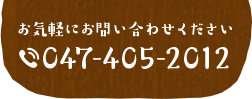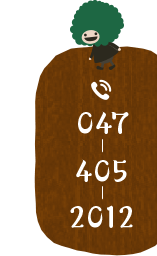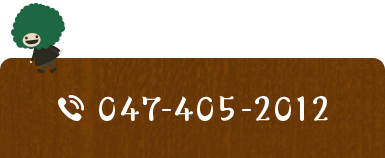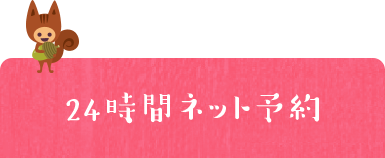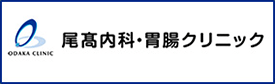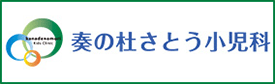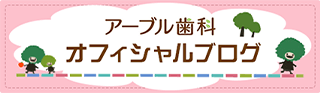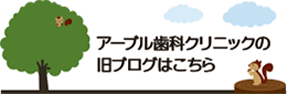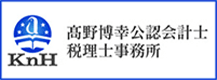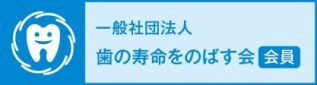インビザラインファーストの痛みはどのくらい?詳しく解説
小学生のお子さまの歯並びが気になり始めた保護者の方へ。「インビザラインファースト」という言葉を耳にしたことはありますか?透明なマウスピース型矯正装置として注目を集めていますが、実際のところ痛みはどうなのか、本当に選ぶべき理由があるのか、気になるところですよね。
当院では多くの保護者様から「子どもが痛がらない矯正装置はないですか?」というご質問をいただきます。特に小学生のお子さまは痛みに敏感で、矯正治療への不安が大きいものです。
そこで今回は、小学生向けのマウスピース矯正「インビザラインファースト」の痛みの実態と、選ぶべき理由について詳しくお伝えします。

- インビザラインファーストとは?小学生向け矯正の新選択肢
- インビザラインファーストは本当に痛くないのか?実態を解説
- インビザラインファーストを選ぶべき理由と注意点
- インビザラインファースト症例
- インビザラインファーストの失敗例と成功のポイント
- まとめ:インビザラインファーストは痛みの少ない選択
インビザラインファーストとは?小学生向け矯正の新選択肢
インビザラインファーストは、小学生(7〜10歳頃)のお子さま向けに開発された透明なマウスピース型矯正装置です。従来のワイヤー矯正とは異なり、取り外しが可能で透明という特徴を持っています。
この装置は、永久歯が生え始めた混合歯列期のお子さまに適しており、歯列の拡大と前歯の整列を同時に行うことができます。特に「装置の見た目が心配」「虫歯リスクを減らしたい」というご要望に応える選択肢として注目されています。
インビザラインファーストの主な特徴
インビザラインファーストには、従来の矯正装置にはない特徴がいくつかあります。
- 透明で目立たない外観:周囲からほとんど気づかれることがありません
- 取り外し可能:食事や歯磨きの際に外せるため、口腔衛生を保ちやすい
- 痛みや違和感が少ない:マウスピース1枚あたりの歯の移動量が最大0.25mmと微小
- 通院頻度が少ない:1.5〜2ヶ月ごとの通院で済む
- 歯列拡大と前歯整列を同時に行える:治療期間の短縮が可能
ただし、適用条件として「第一大臼歯(6歳臼歯)が生えている」「前歯が2本以上生えている」「乳歯がまだ数本残っている」などの条件があります。お子さまの歯の生え変わり状況によって適応するかどうかが変わってきますので、専門医の診断が必要です。
インビザラインファーストは本当に痛くないのか?実態を解説
「痛くない矯正」と聞くと、まったく痛みがないと思われがちですが、実際はどうなのでしょうか?
インビザラインファーストは、従来のワイヤー矯正に比べて痛みが少ないことが特徴です。これは、マウスピース1枚あたりの歯の移動量が最大でも0.25mmと微小に設定されているためです。過度な力がかかりにくく、比較的違和感が少ないのが大きなメリットです。
また、ワイヤーを使用していないため、粘膜に当たる痛みや刺さる痛みはなく、口内炎ができることもほとんどありません。
お子さまが感じる痛みや違和感
実際に当院でインビザラインファーストを使用されているお子さまからは、以下のような感想をいただいています。
- 「最初は少し違和感があったけど、すぐに慣れた」
- 「新しいマウスピースに交換した日は少し締め付け感がある」
- 「ワイヤー矯正をしている友達より痛みが少ないみたい」
多くのお子さまが、初めてマウスピースを装着した時や、1週間ごとに新しいマウスピースに交換した時に軽い締め付け感を感じますが、数日で慣れることがほとんどです。
痛みに敏感なお子さまでも、インビザラインファーストなら比較的受け入れやすいというのが実感です。
痛みを軽減するためのポイント
インビザラインファーストの痛みをさらに軽減するためのポイントをいくつかご紹介します。
- 新しいマウスピースは就寝前に交換する:睡眠中に初期の違和感に慣れることができます
- 冷たい飲み物を飲む:マウスピース交換後に冷たい水を飲むと、一時的に痛みが和らぎます
- 柔らかい食べ物を選ぶ:マウスピース交換直後の1〜2日は柔らかい食べ物を選ぶと良いでしょう
- 正しい装着方法を守る:装着・取り外しの方法が適切でないと余計な痛みの原因になります
当院では、インビザラインファースト治療開始時に、これらのポイントを詳しくご説明し、お子さまが快適に矯正治療を続けられるようサポートしています。

インビザラインファーストを選ぶべき理由と注意点
インビザラインファーストには多くのメリットがありますが、すべてのお子さまに適しているわけではありません。選ぶべき理由と注意すべき点を詳しく見ていきましょう。
インビザラインファーストを選ぶべき6つの理由
インビザラインファーストが特に適しているのは、以下のようなケースです。
- 見た目を気にするお子さま:透明なので周囲からほとんど気づかれません
- 虫歯リスクを減らしたいケース:取り外して歯磨きができるため、口腔衛生を保ちやすい
- スポーツや楽器演奏をするお子さま:活動の妨げになりにくい
- 痛みに敏感なお子さま:従来の矯正装置より痛みが少ない
- 通院負担を減らしたい家庭:1.5〜2ヶ月ごとの通院で済む
- 将来の抜歯矯正を避けたいケース:成長期に顎の骨の成長を促すことで、抜歯矯正を回避できる可能性が高まる
特に、お子さまが「歯並びを治したい」という強い意欲を持っている場合に効果を発揮します。
注意すべき4つのポイント
一方で、以下のような点には注意が必要です。
- 自己管理が必要:1日20時間の装着が必要で、お子さまの協力が不可欠
- 適応条件がある:歯並びや年齢によっては適応できない場合もある
- 治療期間の制限:マウスピース作成可能期間が1年半と限られている
- 費用面:従来の1期治療より高額(50万円+税)
特に自己管理の面では、お子さま自身のモチベーションと保護者様のサポートが治療成功の鍵となります。「装置を使わないと治らない」という大原則を、お子さまにもしっかり理解してもらうことが重要です。
-
-
インビザラインファースト症例


診断名 上顎前突・叢生(小学生の混合歯列期の矯正治療) 年齢 10歳 治療期間 22ヶ月 治療回数 11回 抜歯部位 なし 治療装置 カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザラインファースト) 治療費 ¥450,000 + 消費税(来院時の歯並び調整費用 ¥5,000 + 消費税) リスク・副作用 - 口腔内・歯並びの状態によっては対応できない場合があります
- マウスピース型矯正装置の長時間装着(1日20時間以上)が必要です
- 治療計画通りに進めるために、患者様自身での装着管理が重要になります
- 矯正治療後の保定が必ず必要になります。不十分な場合は後戻りする可能性があります
- 自費診療(保険適用外)となります
-
インビザラインファーストの失敗例と成功のポイント
どんな治療法にも成功例と失敗例があります。インビザラインファーストの失敗例と成功のポイントを知ることで、より良い選択ができるでしょう。
よくある失敗例
インビザラインファーストの失敗例としては、以下のようなケースが報告されています。
- 装着時間の不足:1日20時間の装着が守られず、効果が十分に得られない
- マウスピースの紛失・破損:特に小学生は紛失リスクが高い
- モチベーション低下:治療途中で続ける意欲が低下する
- 不適切な症例選択:適応症でないケースに使用して効果が限定的
特に装着時間の不足は最も多い失敗原因です。マウスピースは取り外しができる便利さがある一方で、「サボれてしまう」という最大のデメリットもあります。
成功のための5つのポイント
インビザラインファースト治療を成功させるためのポイントをご紹介します。
- お子さま自身の意欲:「歯並びを治したい」という本人の意欲が最も重要
- 保護者様のサポート:特に低学年のお子さまは保護者様の協力が不可欠
- 装着時間の厳守:1日20時間の装着を必ず守る習慣づけ
- 定期的な通院:1.5〜2ヶ月ごとの定期検診を欠かさない
- 適切な症例選択:専門医による適切な診断と治療計画
当院では、治療開始前に必ずお子さまと保護者様に詳しい説明を行い、インビザラインファーストが適切な選択かどうかを一緒に考えています。お子さまの性格や生活習慣も考慮した上で、最適な矯正方法をご提案しています。
下記ページからいくつかの症例をご確認いただけます。
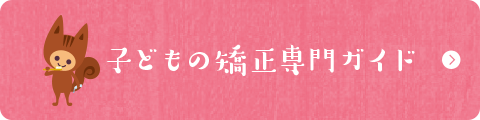
関連記事
まとめ:インビザラインファーストの成功のために
インビザラインファーストは、従来の矯正装置に比べて痛みが少なく、見た目も目立たない小学生向けのマウスピース矯正装置です。取り外しができるため口腔衛生を保ちやすく、虫歯リスクを軽減できる点も大きなメリットです。
ただし、1日20時間の装着が必要で、お子さま自身のモチベーションと保護者様のサポートが治療成功の鍵となります。また、すべてのケースに適応するわけではなく、費用面でも従来の1期治療より高額になることを理解しておく必要があります。
当院では、お子さまの歯並びに関するご相談を随時承っております。「第1期治療」を小学2年生(7歳)ころより開始し、あごの成長時期(7歳〜12歳ころ)に矯正装置を使用して歯並びの土台作りをしていくことをお勧めしています。
お子さまの歯並びで気になることがあれば、どんな些細なことでもアーブル歯科クリニックお気軽にご相談ください。お子さまに「キレイな歯並び」と「素敵な笑顔」を贈るお手伝いをさせていただきます。
著者情報
- アーブル歯科クリニック 院長 田中 雄一
-
略歴
- 2007年日本大学松戸歯学部卒業
- 2007年日本大学松戸歯学部附属病院 臨床研修医
- 2008年~2014年一般開業医勤務
- 2014年アーブル歯科クリニック開院
-
所属団体
- 日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座 非常勤
- 日本口腔インプラント学会
- 日本顎咬合学会
- 日本臨床歯周病学会
- AICインプラント専門医
- BPSデンチャークリニカル 認定医
- スウェーデン歯科学会
- 口腔感染症予防外来認定医
- POIC研究会 ホームケアアドバイザー認定
- 私立アスクかなでのもり第二保育園 嘱託医
- ブレーメン津田沼保育園 嘱託医
- リトルガーデンインターナショナルスクール新習志野校 嘱託医
- クニナ奏の杜保育園 嘱託医
- 習志野市立谷津小学校 学校歯科医
-
矯正医
- 田中 慶子
-
所属団体
- 日本矯正歯科学会 認定医
- インビザライン 認定医